『日経研月報』特集より
調和する未来のために
2025年2-3月号
1. はじめに
前回の1970年大阪万博から55年が経ち、2025年大阪・関西万博が再び大阪の地で開催される。テーマは「人類の進歩と調和」から「いのち輝く未来社会のデザイン」へと移り変わった。進歩も調和もしていないと語った1970年から、未来社会を自らデザインしようという2025年まで変化し、ある種の傲慢さは秘めながらも未来を切り開こうとする意欲的な姿勢を見ることができる。55年間でインターネットや人工知能など技術的には進歩はしたが、社会の分断から紛争までさまざまなレベルでの混乱は無視できないものになってきている。私たちは未来の世界をどのように形作っていくことができるのか、未来世代にどんな世界を残すことができるのかが問われる重要なタイミングになっている。
私自身は、今回の大阪・関西万博では大阪府と大阪市が出展する大阪ヘルスケアパビリオンのディレクターを務めるほか、日本国際博覧会協会がテーマウィーク事業で主催する「アジェンダ2025」の次世代・インクルージョンのプログラムのプロデュースも行っている。いずれも私の担当部分では「人類の調和」を主題に取組みを進めており、本稿ではそれぞれの内容とその背景にある考え方を紹介したい。結論から述べると、「わたし」と「世界」が調和する未来は実現可能なのかという問いが私の人生の主題である。過去には、内閣府と科学技術振興機構が推進する国家プロジェクト「ムーンショット型研究開発事業」の研究開発目標を追加する調査研究に採択され、科学技術による人類の調和という題目で調査研究に取り組んだこともある。
2. バーチャル大阪パビリオン
エンターテイメントによる行動変容
大阪ヘルスケアパビリオンの出展参加テーマは「REBORN」で、私は地元パビリオン出展にかかる構想から企画まで有識者委員として携わってきた。光栄なことに実制作のフェーズでもバーチャル関連の直接的なディレクションをする機会をいただき、大阪府知事や総合プロデューサーのご厚意で、バーチャル大阪パビリオンについては私の物語を最大限に反映したコンテンツ群を制作させていただいている。
バーチャル大阪パビリオン「ユーダイモニア」は未来的な世界を描いた物語と舞台であり、シナリオを基軸とした小説や漫画、バーチャル音楽ライブ、メタバースなどのコンテンツを多層的に構築する。ユーザーはそれらをエンターテイメントとして楽しんだり、アバターによるライブ配信を通じて体験したりすることにより、いつの間にか物語の一部になるような(代替現実的な)かたちで没入していくことになる。その背景にあるのは、エンターテイメントによる行動変容こそが若者に必要だという発想である。そういった「面白い」「楽しい」という経験を通じてしか心に働きかけることはできないと考えている。

ヘルスケアや人工知能が発展するほど私たちは「データ駆動型社会」の未来に向かっていく――ということがシナリオの背景にある。SNSやネットニュース、ECサイトでの情報の推薦はもちろん、ウェアラブルデバイスによる生活改善のアドバイスまで、最先端のテクノロジーのおかげで私たちは複雑な社会における意思決定、ひいてはその先の合意形成までスムーズにできるようになっていくであろう。ただし、それらは常に誰かに悪用される危険を孕んでいるうえに、もし私たち個人の幸福に資するものだったとしても、そこに自由意志はあるのかという問いは残される。幸福とは何か。運命とは、自由意志とは何かといった中学生や高校生には難しい問いを、この「ユーダイモニア」という物語を通じて考えてもらうことを目指す。
この物語はまさに万博会期にかけて順次展開されていくもので、この場で全貌を紹介することはできないが、その舞台について少し補足する。この未来的な都市にはヘルスケアデバイスと人工知能があまねく普及しており、街中にはメディアビジョンが張り巡らされている。人々の意識・無意識的なデータがデバイスを通じて集められ、一人ひとりの健康で幸福な意思決定が人工知能により支援されているという未来である。人々の緩やかな合意形成を支援するために人々への緩やかな働きかけ(フィードバック)も行われ、結果として分断や対立がなくなっている。これらはあり得たかもしれない「人類の調和」が実現した未来都市である。
運命と自由意志
テクノロジーに下支えされた穏やかな調和は、社会主義の問題を改善したものに近いかもしれないし、利益を享受する特定の集団が存在しない管理社会かもしれない。要するに、現状の思想的枠組みでは一言でその問題を指摘するのが難しいユートピアを描こうとしている。『すばらしい新世界』のように階級社会やドラッグも存在せず、『1984年』のように監視・歴史修正されているわけでもない。もちろん本も焼かれていないし、個人の人生も予め決められているわけでもない。ほんの少しだけ緩やかに、個人の幸福と社会の幸福が重なり合うように支援されているというだけである。
そのようなキュレーションされた運命と対になる概念として、自由意志を取り上げる。それは私の人生は私が決めるという強い意志であり、推薦アルゴリズムが可処分時間を奪い合う現代においてもすでに失われつつある。人々の行動は緩やかにキュレーションされていて、かつての戦意向上のためのメディアミックスよりもよほど狡猾かつ深刻に私たちを蝕んでいる。オンラインでショッピングするとき、タイムラインでニュースを読むとき、それらに反応して行動を起こしたとき、どこまでが私の判断だったのか切り分けるのは難しい。それに対して、自分の意思を見出したいという理想も成立するはずだ。
緩やかにキュレーションされた都市は、音楽を奏でるように人々に影響を与えている。その枠組みから、都市のキュレーションの枠組みから外れるためのトリガーが「歌」である。未来都市に対して反旗を翻す歌姫がゲリラ音楽ライブを行っていくことで、人々が自由に目覚めていく。自分の内面に隠れた欲求を思い出し、他者との比較を思い出し、表現を思い出すというイベントであり、私たちはそのバーチャルライブを実際に楽しむことができる。自由意志を強く自覚して行使することには強烈な負荷が伴ううえに、他者との分断はテクノロジーなしでは埋まらない。簡単に言えば、寛容であるための努力は個人に対して課される。しかし、それでもなお私は自由を求めるのだという姿勢が未来都市に対応する勢力のビジョンである。歌姫を中心とした宗教的とも言える熱狂、損なわれるものがあったとしても自分の人生を自分で決めようという強い意志が示される。
個人と集団の幸福が重なり合う「人類の調和」について考えるため、この物語の中では理想化された二つの立場をキャラクターに代弁してもらう。自由意志・個人・「今」を代表する歌姫。運命・集団・「未来」を司る研究者。ユーダイモニアを駆ける二人の物語を追いかけることが未来社会を想像することにつながる。二人のうちどちらとのエンディングを望むか、バーチャル大阪パビリオンの来場者の投票によって決定することで、自分たちの選択が未来の社会をつくるのだという実感を持ってもらうことも仕掛けとして企画している。この物語を通じて若者に未来を問いたいと考えており、バーチャル大阪パビリオンとは社会実験そのものだと言える。
3. シェイプニューワールドイニシアティブ
未来社会のデザイン
もう一つは、まさに未来社会のデザインを主たる目的とした「シェイプニューワールド」という取組みである。日本国際博覧会協会と、世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)の33歳以下の若手で構成されるコミュニティ(グローバルシェイパーズコミュニティ)のメンバーとのコラボレーションで立ち上がったのが「シェイプニューワールドイニシアティブ」である。石川勝プロデューサーとともにこのイニシアティブの立ち上げを行い、代表を務めさせていただいている。
未来を選んでいく様は山登りにも似ている。計画も地図もなく山登りをするのは危険である。綺麗な花を摘むために野原を歩き、水を汲むために沢まで降りて、見通しのいい丘を目指す頃には遭難している。目指すべき山を決め、その山頂に至るまでの適切な道筋を想定して地図を描き、地図に沿ってコンパスを持って進むことが必要で、良い未来に向かうためにも同じ考え方が必要になる。
未来はまず想像することで、初めて創造することができる。短期的な視座から研究開発や社会実装をしていると、SF小説『すばらしい新世界(Brave New World)』のように、高度な技術に恵まれながらも不幸な人々で溢れるディストピアに至ってしまうかもしれない。フォーワードの方向だけでなく、良い未来からバックキャストした計画をつくる、そのためにBrave New Worldに対する「Shape New World」を立ち上げた。
より専門的な言葉で紹介すると、私たちは未来世代にどんな世界を残せるのか、過去から現代に影響を及ぼしたバタフライエフェクトが話題になる一方で、現代を生きる私たちが未来に対してどれだけの影響を与えうるのかについては無自覚である。世代間倫理を見据えた長期主義的な視点に立ち、どんな未来を選んで、行動して、残していきたいのか、2025年大阪・関西万博の機会に真剣に向き合いたいと思いイニシアティブでの活動を進めている。
地球的規模の課題に向き合う
シェイプニューワールドイニシアティブでは、「未来社会デザインに係る調査研究」と「未来社会創成委員会」の二つの取組みを推進している。いずれの取組みでも、未来を主体的に選択するという姿勢をもって2050年の未来社会ビジョンを設定し、現代からその未来にいたる道筋をバックキャストすることで世界の主要課題を整理する。そして、科学技術や医療の進歩、政治や経済を含む社会システムの変革による解決策を策定していく。さらには、そのロードマップを現実のものにするための産学官民の具体的な行動指針も提案する。それらの取組みの中心として、2025年大阪・関西万博のテーマウィークにおける全8テーマにわたる24個のセッションの企画運営が主要なアウトプットとして設定されている。
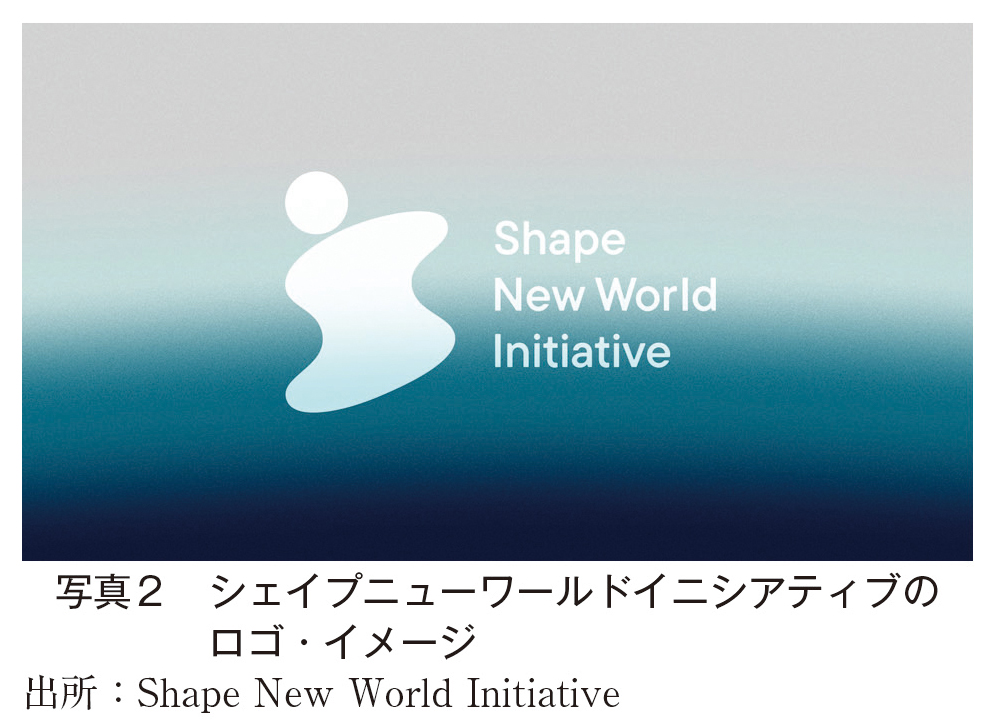
未来社会デザインに係る調査研究では、大阪大学と科学技術振興機構の共同研究プロジェクトとして、国内のアカデミアや各業界のトップランナーを招いた調査研究に取り組んでいる。アカデミアとイニシアティブが連携した科学技術による未来社会のデザインの取組みであり、調査研究報告書は政府機関等への提言に役立てられるほか、テーマウィークにおける議論の重要な基盤となる。大阪・関西万博の会期前までに調査研究報告書を取りまとめ、テーマウィーク「アジェンダ2025」でその成果を発表する。
未来社会創成委員会は、世界経済フォーラムのグローバルシェイパーズコミュニティに所属するメンバーが中心となって進行する議論の場であり、若者らしい独創的な視点や海外のシェイパーとの交流を通じた多様性のある視点から未来のビジョンの提案を行うものである。各テーマでグローバルシェイパーズと有識者が議論を行う分科会を大阪商工会議所と開催し、議論を通じて未来像を描きながら、テーマウィークにおけるプログラム案を策定していく。
なお、テーマウィークとは、世界中のリーダーや有識者が半年間にわたり同じ場所に集う万博の特性を活かし、地球的規模の課題の解決に向けて英知を持ち寄り、対話による解決策を探り、いのち輝く未来社会を世界と共に創造することを目的として行う取組みである。約1週間(10日間)ごとに地球的課題をテーマに設定し、解決策を話し合う「対話プログラム」と行動のための「ビジネス交流」などが実施される。
本イニシアティブでは未来社会デザインに係る調査研究の研究代表者と未来社会創成委員会の座長として全体的な取りまとめを行っているが、八つのうちの個別のテーマ「SDGs+Beyondいのち輝く未来社会」も担当している。具体的な内容は、ほか七つのテーマやそれに至るロードマップを明らかにしたうえで、どうすれば私たちがその未来を目指すことができるのかというものである。すなわち、テクノロジーに支えられた社会システムのあり方や意思決定、合意形成のプロセスなどが対象になる。これはバーチャル大阪パビリオンにも通底する議論である。
4. 人類が調和する未来へ
冒頭で述べたように、私が目指しているのは人類の調和である。この「わたし」と「世界」が調和する未来という主題は、まだ大学生だったときに出会った二つの作品から得た。伊藤計劃というSF作家が残した『ハーモニー』という作品と、アルフォンス・ミュシャによる《ハーモニー》(1908)という作品である。星雲賞や日本SF大賞、フィリップ・K・ディック賞特別賞を受賞した『ハーモニー』は、SF作家のみならずさまざまなクリエイターや研究者に影響を与えている。社会のリソースとしての身体、個人の意識と集団の維持、データによる健康・幸福社会などが扱われており、バーチャル大阪パビリオンは本作(および前作の『虐殺器官』)へのアンサーソングである。後者はアルフォンス・ミュシャによる横幅五メートル近い大型の油彩画である。丘に集まった人々に大いなるものが光を与えており、叡智を持って調和をもたらす神秘的な様子が描かれている。私たちは調和に向かうことができる、信じることができると確信させられる迫力がある作品である。
そういった作品に触れると、「わたし」と「世界」は調和していたのだと信じることができる。実際、個人と集団の幸福が両立する未来社会を思い描き、皆がそれを信じて向かうことで、想像上の物語ではなく来るべき未来にすることができるのだと考えている。未来社会のデザインとは、大いなるビジョンを私たち自身が実行していくことにより、望むべき未来を手に入れるというプロセスを指すのであろう。ムーンショット型研究開発事業や未来社会デザインに係る調査研究などの一連の調査研究は、私にとって現実の世界と物語をつなぐ架け橋として機能するものである。
「人類の進歩と調和」から「いのち輝く未来社会のデザイン」へ。続く2025年大阪・関西万博では、これらのコンテンツを一緒に作り上げてくださっている皆様と、コンテンツや成果を体験してくださる皆様と、これらの問いを共有したいと考えている。この文章を読んでいただいた皆様にも、ぜひこの万博を機に、一緒に調和する未来について考えていただきたい。

 地域
地域 